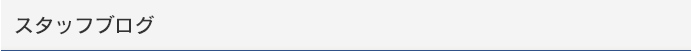個人から現金や不動産など価値のあるものをもらった時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり(みなし贈与財産)、債務を免除してもらったときにも贈与税は適用されます。
個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
贈与対象資産は、
現金、預貯金、有価証券(株式)、土地、家屋、貸付金、営業権など
金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
なお、贈与ではあるが非課税とされるものがあります。
例えば、扶養義務者からの生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど
社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の申告時期は、原則、財産をもらった人が、
その年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
「贈与税は相続税の補完税」と言われており、相続税との関係が深い税金です。
これは、相続税がかかる人が死ぬ前に財産を全て贈与してしまうと、
相続税の課税対象となる資産がなくなり、結果として相続税逃れになってしまうためです。
相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)以下の財産を持つ方でも、
贈与税は110万円を超える部分に対してかかってくるのです。
そしてこの贈与税の税率は、相続税に比べて高くなっています。
1,000万円を超える贈与については、40%という高い税率で贈与税が課税されてしまいます。
しかし、生前贈与は相続税の節税対策の主たる対策方法です。
様々な施策を融合することで、多額の相続税を節税することが可能となります。
また、生前贈与を行う方の中には
「相続税は関係ないけれど、生前からできる限り次の世代に財産を移しておきたい」
といったご要望もあることと思います。
生前から、コツコツと対策を行うことで、相続税を大きく節税できます。
・生前贈与は3年内であれば相続財産に加算
相続などで財産をもらった人が、
被相続人が亡くなる3年以内に贈与を受けた財産があるときには、
贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算しなければなりません。
・預金にも注意を
贈与が相続開始前3年以上経過していたとしても、
相続税申告において、名義預金として計上することを求められるケースがあります。
贈与と認定されるためには、口座間で預金を動かすだけでは不十分な場合もあります。
次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、
法人から財産をもらった場合には所得税がかかります。
生活費や教育費として受け取っていても、
有価証券や土地などの目的以外の用途でつかった場合には、贈与税が課税されます。
①「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物及び見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
②「直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の条件を満たすもの。」※限度額があります。
③「地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人及び扶養する人が、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利」など
時価よりも安い価格で売買した場合に贈与税が課税されます。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。
例えば、ある人が時価1,000万円の土地を子供に300万円で売却したとします。
しかし、他人との取引の際、土地を時価の半額以下で売ることはまずありません。
この場合、
息子は親から700万の贈与を受けたとみなされ、700万円に対して贈与税がかかります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額を、
その翌年の2月1日から3月15日までの間に課税価格、贈与税額等を記載した申告書に、
一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
財産をもらった人が申告することになっています。